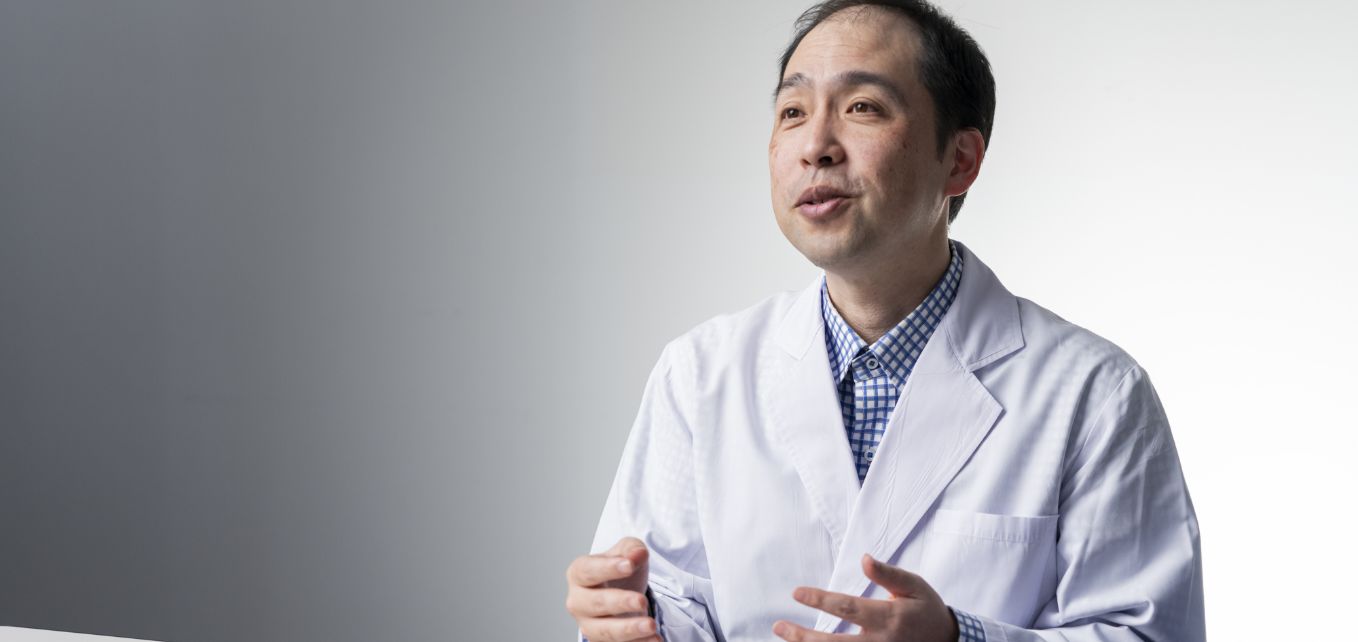2014年10月10日虫
アオスジアゲハを育ててみよう(後半)
昨日の最後の写真ですが、中心の幼虫に視線が行きますが、
もう1匹いるのに気付きましたか?
さて、幼虫は緑型になり3cmを超えたら食欲が凄いです。
飼育していたら毎日葉っぱ調達をしなくてはなりませんので、屋外飼育を継続です。
ただ、4cm位になりますと、いよいよ蛹になる日は近いので捕獲。
持ち込み初日は旨そうに葉を食べていたのですが、
次の日からピタッと食べなくなりました。
環境変化によるストレスかと心配し、より新鮮な大好物の若葉を持ち込んでも食べません。
初日はむしゃむしゃ食べていたことを思い出し、出した結論は、
「もうすぐサナギになるな」
こんなタイミングで室内に入れるなんて私の感はなかなか鋭い!
サナギの写真ですが、最初はどれか気が付かないのでは?
写真中央です。
完璧な擬態!
葉脈まで見事に再現されています。
これが自然界だと、更に沢山の葉っぱが重なっているので、そう簡単には見つかりません。
進化って不思議過ぎる。
放置しておくと、存在を忘れかけた頃に羽化します!
捕獲した成虫とは異なり、翅は全く欠けたり傷ついたりしておらず、とても美しいです。
蝶の標本マニアはこうやって自作で美しい個体を作ります。
ちなみに、私は標本は作りません。
たまに幼虫時代に寄生バチが体内で育っている場合があるので、ホッとします。
サナギの中から、小さいハチがたくさん出て来る現象はSF映画の世界ですからね。
ただ、羽化の観察のために室内で飼育したのに、またも気付かず。
来年以降の課題です。